関連文献の紹介「臨死体験」
臨死体験を初めて統計的に研究した記念碑的著作。アメリカでベストセラーになり、その後、臨死体験の学問的研究が加速した。
ムーディは50人程の臨死体験者と面接し、その人達の体験をもとにしてこの本を著わしている。
以下に要約を示す。
「死に瀕した時の状況や死を体験した人々のタイプが、多種多様であるにもかかわらず、体験内容そのものには驚くほどの共通点がある。その共通している要素を拾い上げてみると全部で十数個になる。
これらの要素をすべて一度に体験した人はいないが、大抵は八ないしそれ以上の要素を体験している。
これらの要素を次に列記する。
-
言葉では体験は表現できないということ。
その他の要素を起こる時間的順序に従って記すと、 - 死の宣告が聞こえる
- 心の安らぎと静けさがある
- 耳障りな音が聞こえる
- 暗いトンネルを猛烈な速度で通り抜ける
- 物理的肉体を離れる
- 既に死んだ肉親や友人と会う
- 『光の存在』と出会う(完璧な愛に包まれる)。キリスト教徒はこれをキリストと見、ユダヤ教徒は天使と見、無宗教の人は単に光の存在と見る。
- 人生回顧。自分の一生を『光の存在』がパノラマのように写し出して見せてくれる。これは責める為ではない、自己の成長の為である。
- 境界あるいは限界に近づく(現世と来世の境)
- 蘇生する(現世には戻りたくないのに意に反して)
- 死の体験を話そうとするがうまくいかない
- 人生に大きな影響を受ける
- 死に対して新しい考え方を持つようになる(死を恐れなくなる)。
このように天国や天使たち、あるいは地獄や悪魔などについて語った人は一人もいない。ほとんどの報告において、報酬と懲罰からなる来世像は否定されている。臨死体験者の多くは、古い観念と引き替えに、死後の世界に対する新しい観念と理解を携えてこの世に戻って来るようである。つまり、一方的な断罪ではなく、自己成就という究極の目的のための発展といったビジョンを持ち帰るようである。」
死後の世界はバラ色だけではないということ、暗黒の苦しみの世界もあるということを警鐘乱打している本。
この本の著者は心臓病の専門医であり、救急病院で多くの患者の蘇生を手がけてきた。患者の生の声を、生き返った直後に聞いたという点で今までのレポートと大きく異なっている。
著者によれば、蘇生した人の20%しか自らの体験を語りたがらなかったが、語った人は、素晴しい体験をした人と恐ろしいところへ行ってきた人と半々だったという。
面白いことに、恐ろしい体験をした患者に数日後にもう一度聞いたところ、全く記憶に残っていないと言う。人間の記憶は自己防衛本能からか、苦しい記憶を消去してしまうらしい。
従って、今までの調査のように臨死体験者に後日、話しを聞くのでは正確な結果は得られない。今までの報告がいい体験ばかりだったのはこの為だという。
2)同様、死後の世界はバラ色だけではないということ、暗黒の苦しみの世界もあるということを警鐘乱打している本。
この著者は不幸の連続の、なかば自暴自棄の半生を送ったあげく自殺する。ところが未遂で臨死体験をして生き返ってくる。その体験をまとめたのがこの本である。
彼女は暗黒の空間に無限に広がる暗い平板の端に降り立つ。その板の上にはそれこそ何十万という人が群がっている。そこでの苦しみは生きている時に味わった苦しみの比ではなかった。
そこにいる他の大勢の人達は皆、自分のことに完全に没頭していて、全く他の人のことが眼中に入らない。ぶつぶつ独り言を言ったり、自己弁護に懸命で、そこでもう何年も同じ弁明を繰り返しているように見える。時間というのは地球上での概念で、ここでは一日が千日でも、千年でもありうる。彼女も急速に他の連中と同じようになって行くのを感じた。ここは希望が死ぬ世界である。
彼女はこの暗黒の世界から、二人の『光輝く存在(彼女はこれを神とキリストと認識している)』によって救い出されて、この世に帰って来る。この時、彼女はこの『光』からいろいろなことを学ぶ。そのいくつかを紹介したい。
その『光』は彼女の人生を今までいっしょに生きてくれていた。彼女は今まで自分の苦しみは誰もわかってくれないと思っていたが、その『光』は彼女の苦しみを共に味わって来てくれていたのだ。この世での苦は決して無駄ではなく、成長のもとになるが、地獄での苦は意味がなく、無限の責め苦である。地獄はこの世で作った罪を償うために行く。ほとんどの人は死ぬとこの暗黒の世界へ行く。
人間は肉体と、霊と『光と闇』から成り立っている。自分の行為(心で思うことも含む)によって、光が増したり闇が増したりする。善をすると光が増し、悪をすると闇が増す。光と闇しかなく、その中間はない。
彼女の心は闇で覆われていたので、暗黒の世界から出られなかった。光を見るためには心の中に光がなければならない。彼女がこの暗黒の世界から出られたのは、彼女に神を信じたい、光を見たいという意志があったからだという。意志と能力は同じで、信じようとしたので光を見ることができた。信じようとしない人は、この暗黒の世界から永遠にでられない。
地球以外にも無数に神の子の住む世界があり、それは皆それぞれの太陽のまわりを回っている。神自身、我々の世界と同じような世界で生きたことがあり、善を修め悪を退けて、道を進んだ。この言葉に彼女は驚く(キリスト教の教義と異なるから)。
ここで興味深いのは、神も地球のような世界で道を究めてきたこと、地球以外にも無数に生きとし生けるものの住む地球のような世界があるという点で、これはキリスト教の教義とは全く違う。むしろ仏教で言っていること、特に阿弥陀経等に説かれていることに一致している。
彼女が遭遇した二人の「光輝く存在」はモンロー研的解釈をすれば、ガイドやヘルパーと呼ばれる存在である。彼らは人の信仰に合わせた姿で現れる。この本の著者はフォーカス23的な場所に囚われていたことになる。
情報量の豊富さ、その分析の緻密さに於ては他に類を見ないものがある。また、日本では従来、この分野はオカルト的興味での出版物がほとんどを占めていて、真面目な研究者からはタブー視されていた。その中、臨死体験の日本に於ける研究を学術的レベルにまで引き上げた意義は大きい。ただし、この本は順序良く整理された形に(つまり教科書のように)書かれているわけではないので、若干読みにくさはあると思う。
まず今までの各種の報告についての詳細な解説がなされている。ムーディの本の紹介と、「その問題点を指摘しかつ補った」ケネス・リングの本の紹介をはじめ、現時点までに得られた種々の情報を総括している。 と同時に、日本、アメリカ、インドでの調査データに基づいての検討、異文化での臨死体験の共通点と相違について検証している。ただしこの本には臨死体験のネガティブな面の報告例はあまり出てこない(出てきても精神的な影響はポジティブだとする)。
この異文化での比較で興味深い点は、この三国での体験にかなりの隔たりがある点である。たとばアメリカの体験者は光を見る率が高く、しかも光を神あるいはキリストなどと把握するが、日本では光を体験する率が低い上に、それを神的なものと言う人は皆無である。インドでは光の存在との出会いそのものが全くない。その代わりにヤムラージ(えん魔大王)に会う。また日本では三割近い人が三途の川に出会っているが、欧米では非常に少数である。
このことから、臨死体験のかなりの部分は、頭の中で作られたイメージ体験ではないのかと指摘している。ただし、これではどうして体験に共通の構造があるのかが説明できないとも指摘している。このように本書は臨死体験が「脳内体験」か「現実体験」かの議論に主眼を置いている。
まず、脳内体験説で臨死体験のほとんどの要素が説明できるという。ペンフィールドやパーシンガーの研究から側頭葉に人工的に電気的刺激を与えることで臨死体験のほとんどを再現できることがわかった。ただし脳内体験説で唯一説明できないのは臨死体験者が遠くで起こっていることを見ていたという事実、つまり見えるはずがないものがなぜ見えるのかということである。また臨死体験を起こす脳のメカニズムをきちんと解明してはいない、という問題点を抱えているとする。ただし前者は、他の手段で得た(たとえば耳で聞いた)情報を元に頭の中で作り出された可能性も否定できないとする。
一方、現実体験説にも矛盾点がある。それらは
- 体験の具体的内容に個人差と文化による差がありすぎる。
- 瞬間的に違うところへ移動できるのは何故か。
- 魂それ自体に視覚、聴覚の感覚能力、考える能力、感じる能力がすべてそなわっていることになるが、それでは感覚器官や脳などというものはそもそも何のためにあるのか。
- 臨死体験で生きている人に会うことがあるのは何故か。
- 事実と合わないことを見ることがあるのは何故かという点である。
結局、議論百出のあげく『ウィリアム・ジェームズの法則』に帰してしまう。つまりどちらとも結論が出ないというのが、この本の結論ということになる。
この調査を通じて著者自身、どちらの説が正しくても大した問題ではないと思うようになったという。
「現実体験説のいうようにその先に素晴らしい死後の世界があるというなら、もちろんそれはそれで結構な話である。しかし、脳内現象説のいうように、その先がいっさい無になり、自己が完全に消滅してしまうというのも、それはそれでさっぱりしていいなと思っている(立花隆「臨死体験(下)」(文藝春秋)」
立花氏は、臨死体験が現実体験でも脳内現象でもどちらでもよくなったと言っている。その理由の一つとして、臨死体験者の言が正しいなら死後には素晴らしい世界があるからとしている。しかし、Maurice Rawlings, M.D.とAngie Fenimoreの二冊の本が示しているように、その結論は正しくない。素晴らしくないケースも多々あるからだ。死の問題についてどのような結論を導こうが、それは個人の責任として自由だ。死は個人が一人で対面しなければならないという意味で、純粋に個人の問題だからだ。しかし、今この段階で熟慮するのを放棄してしまうと、死の直前になって間違っていたことがわかっても、もう取り返しがつかないことだけは、覚悟しておかなければならない。
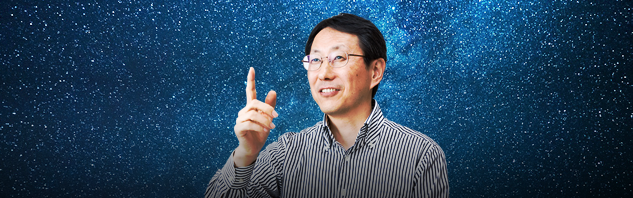
この本によれば、死後の世界は思ったよりもバラ色で恐ろしいところではないというのが、ほとんどの臨死体験者の話しということである。
私は、臨死体験者の体験談を基として死後の世界全体を語るのは、限界があると考えている。臨死体験とはあくまで生き返ってきた人がしてきた体験であって、本当に死んでしまった人のものではないからだ。これは隣国の実情を知るのに、国境沿いの様子だけから判断しているようなもので、本当のところは、中まで入って隈無く見て回らなければわからないのと同じだ。
また生き返った人と死んで帰って来なかった人とで、体験そのものが本質的に異なる可能性もある。次のたとえで理解してもらいたい。
あるところに花の咲き乱れる草原があって、そこにはライオンが潜んでいるという。何人もの人がそこに迷い込んでしまい、帰って来なかった。ただ極くわずかだけ帰って来た人がいた。その一人は言う。
「お花畑のようにとてもきれいなところだった。太陽が明るく輝いてぽかぽかと暖かだった。ライオンなんていなかったし、あそこはとてもすばらしいところだ。」
帰って来なかった人は皆ライオンに食われてしまったのだが、私たちはその人たちの話しを聞くことはできない。